

第4回講座 スキルアップ講座~企画づくり~
日 時:2025年10月11日(土)10:00~15:00
場 所:大謝名区公民館(宜野湾市大謝名5-10-1)
参加者:塾生7名/事務局6名
講 師:平良 斗星 氏(公益財団法人みらいファンド沖縄 副代表理事)
企画づくりについて学びました
第4回講座「スキルアップ講座~企画づくり~」では、公益財団法人みらいファンド沖縄の平良斗星氏を講師にむかえ、現在宜野湾市で展開している認知症の方の見守りシステム「ミマモライド」や、地域の高齢者のライフヒストリーを聞く古写真イベントなど、実際に平良氏が企画から手がけた事業の実例を交えながら企画のつくり方についてお話いただきました。個人の困りごとを課題化し社会で受け止めるためには、誰が何をどのように困っているのか?何を解決したいのか?について具体的に考え、企画の前に問題設定をし、企画書を下支えしていく論拠を積み重ねるための調査をしていくことが大切だということを学びました。それぞれが考える地域の課題について、誰がどんなことで困っているのか、地域の自治、公民館のあり方と結び付けてチームで話し合いを行いました。
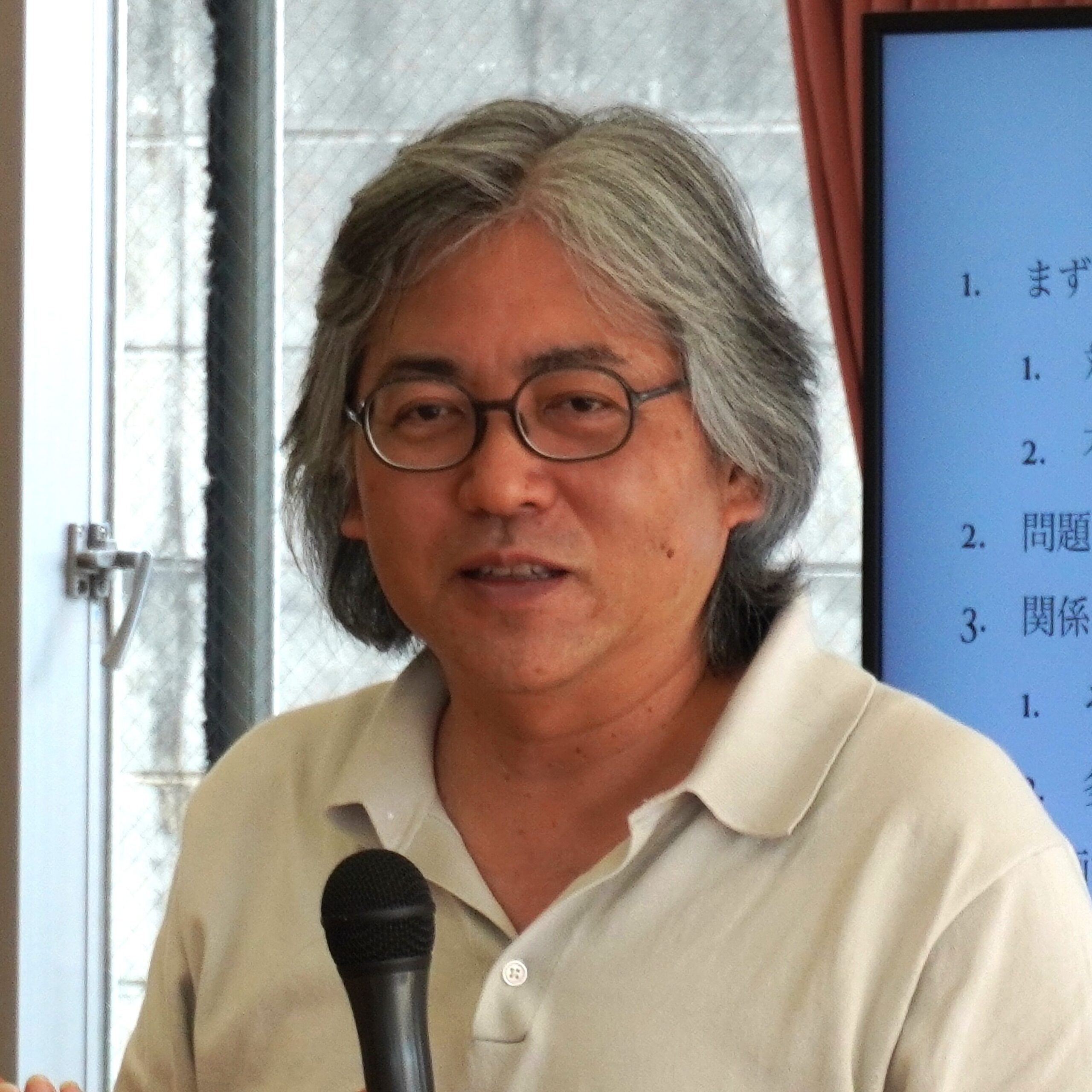
本当の課題とは…?
現在多くの自治会が挙げる問題のひとつに「自治会加入率の低下」があります。ぎのわん地域づくり塾の公開講座として行った、地域円卓会議でもこのことは議論になりましたが「地域の人が自治会に参画していない」ということが本当の"課題"といえるのか?誰の困りごとなのか?それぞれのチームで考えてみました。すると、そもそも自治会と住民とがお互いに見えず、誰が何に困っているのかがわからないことこそが課題なのでは?といった意見や、地域と人のつながりが希薄化することで、文化継承の衰退や孤立化がすすむのでは?といった懸念、他にも、子育て世代にとって公民館を子どもの居場所として使えたら助かるのでは?などの意見が出てきました。
「自治会加入率の低下」というひとつの起こっている事実を掘り下げて考えてみると、そこにはさらにさまざまな問題が見えてくることがわかりました。


企画書の基本
企画づくりの基本としてフォーマットを元に、1枚にまとめる企画書の構成について学びました。企画書は、「タイトル」とそれを補完する、少し中身がわかるような「サブタイトル」をつけることで読む人の印象に残りやすいということでした。その次に「目的」⇒「背景」という順番で書くと、何をしたいのかが伝わりやすく、続く「内容」はシンプルな箇条書きでも良く、しかし重要な順に示すことが大切だということを学びました。さらに必要となる「コスト」(人・建物・お金などの)については、全ての情報を明示し、お金のことであれば総額を書くことで、相手にきちんと判断してもらう材料となるということでした。「現状」は、これまでの取り組みの進み具合いを示すことが、PRにもなるということ、最後の「要望」では、相手に何を求めているのかを明確に記すことも重要だということがわかりました。また、ひとつの企画をブラッシュアップしていくごとに書き直していくために、日付を入れてバージョン管理を行うことも大切だということを学びました。
講座の後半では、チームで取り組みたい課題と企画の方向性を話し合いました。その課題に関わるステークホルダー(関係者)を列挙しながら、平良氏より、ステークホルダー同士がうまくいっていないところを考えたり(構造分析)、対象者と資源(人・場所など)の組み合わせることで、一つの課題に対しいくつも企画が立てられることや、同じ企画でも目的の設定で成果が変わることも学びました。

方向性:地域の方の困りごとを知りたい。気軽に公民館に来てもらいたい。
目的:地域の30~40代の人達の困りごとを知りたい。既に公民館に来ている人たちとじっくり話す時間を持つことで、困りごとを聞き出せるのでは?資源としてカフェ、バリスタさんを組み合わせることで公民館の滞在時間が長くなり、じっくり話す時間がとれるのではないか?

方向性:対象は、小学校低学年の子どもと親。子どもの預け場所や遊び場を増やしたい。学童探しに苦慮している共働き世帯の親を助けたい。
目的:宇地泊公民館はご年配の方の利用が多く、子どもはあまり活用できていない。学童が合わない子どもたちが、気軽に公民館を利用できるようにしたい。自治会と子どもたちの交流を通して関係性をつくっていきたい。公民館の利用に関して、お金がかかる部分を明確に知ることで、やれることが整理できると思う。市民協働課からの助言がほしい!
塾生の声
・問題の根幹がなにか、関係者は誰か、の部分を丁寧にやっていないと感じました。(これまでの企画や事業実施で)そこを丁寧に行っていきたいです。
・企画書の書き方はもちろん、困りごと、目的をまず決めるという考え方は、今日から生かせると思います。収穫の多い日でした。
・企画書を作成するということのハードルが少しだけ低くなった。楽しいアイデアをみんなの力をかりて、生かしていきたい。
・企画をつくってみたいと思います!ステークホルダーと当事者の関係性をよみとく←これについても考えてみます。
以下から上記内容をまとめたNewsLetterをダウンロードいただけます。
第5回は ➡ 「ゼミ チームで企画づくり」
日時:2025年10月17 日(金)19:00~21:30
場所:大謝名区団地自治会事務所(宜野湾市大謝名5-23-1)
第3回講座の報告はこちら